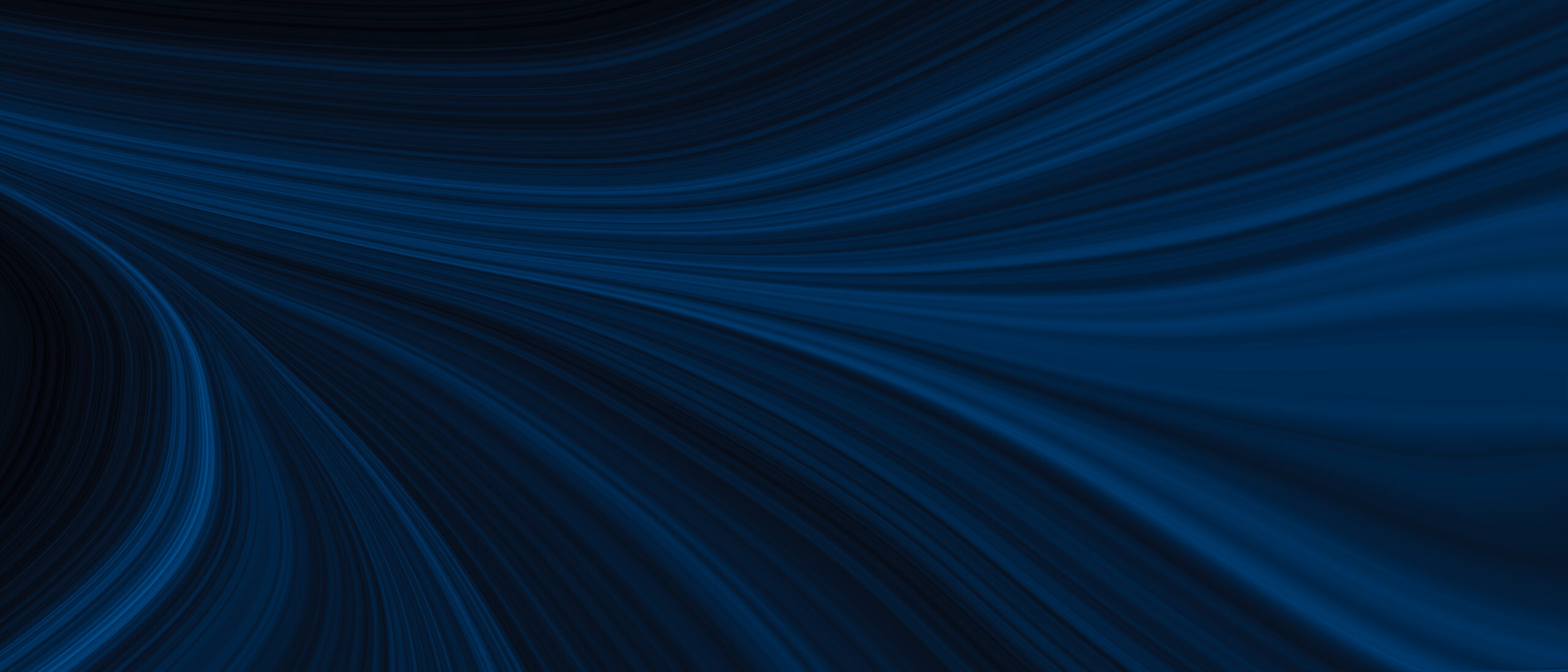定員50名のみ。2万レッスンの実績で、あなたの曲を形に。
シン・東京音楽教室
音楽のスキルは、生涯にわたってあなたを豊かにし続ける、価値ある財産です。
実際、音楽に長けた人ほどそのことを強く実感し、喜びに溢れた人生を送っています。
しかしながら、思い通りに音楽を作れるようになるための道のりは決して容易ではありません。
だからこそ私たちは、その過程にある方々に質の高い学びを提供したいと願うのです。
当教室のミッションは2つ
- 日本のアマチュア音楽クリエイターのレベルの底上げ
- 明日のエンターテイメントシーンを担うクリエイターの育成
クラシック系の音楽大学の作曲科では、エンターテイメントとしての音楽(ポップス、映画音楽、ミュージカル、ゲーム音楽)の作り方は学べません。そもそもが調性音楽の作り方など教えていません。現代において芸術作品としての音楽の作り方を学ぶ場です。
かといって専門学校の講師は、現役のプロではなくいわゆる「レッスンプロ」が大半を占めています。クライアントの意向を正しく把握し、たとえ短い納期であっても、納得してもらえる楽曲を締め切りに間に合わせられればプロとして通用するはずですが、それができないのに講師をしている人達がたくさんいるわけです。
昨今では、プロでありながらスキルマーケットサイトなどに登録し、音楽制作の仕事の合間を利用してレッスンを行うクリエイターが増えてきました。この日本において、音大と専門学校の間を埋める存在として大いに貢献していることは非常に喜ばしいことです。しかしながら一方で、プロやセミプロを自称する「ほぼアマチュア」のサービスが溢れかえっていることもまた事実です。音楽理論やその”教え方”を満足に身に付けていない指導者、”作曲を教える”ことができない指導者、そういった多くの指導者が溢れる中で「本物の指導者」に出会える確率は非常に低く、ほぼ運といっても良いでしょう。
このような時代において、初心者から丁寧に教えることのできる豊富なキャリアを持ち、かつプロを育成できる確かな実力と間違いの無い知識を提供できる現役のクリエイターが、音楽制作事務所という確かな実績と信頼を備えた運営母体のもと、上記2つのミッションを掲げてレッスンを行っているのが、この『シン・東京音楽教室』です。これを読んでいる時点であなたが運に恵まれていることは、この教室のレッスンを受講している生徒のほとんどが認めるところでしょう。
シン・東京音楽教室が選ばれるワケ

アマチュアクリエイターの方へ
「動画やブログで情報を集めても、なかなか上達しない…。」 当然です。なぜなら、情報というものは “一方的な提示” であって、あなた自身へのアドバイスが含まれていないからです。
学んだことを実践し間違いを指摘してもらう。うまくいかない理由を教えてもらう。再び挑戦し、さらなるアドバイスを受ける…。このサイクルを繰り返さなければ、確実な成長は望めないのです。よほど音楽に対するカンの良さと、持って生まれた学習の能力の高さが無ければ、音楽の独習が中途半端に終わるのはそのためです。
当教室では、経験豊富な現役クリエイターの講師が、マンツーマンの丁寧なレッスンであなたを上達へ導き、あらゆる悩みを解消します。さらに、年に二度のMPCの開催や、フォーラムの設置など、モチベーションの維持や、確実なスキルアップのための環境を整えています。
あなたが今現在どんなスキルであったとしても、そこから最高の状態へと導けるだけの準備とカリキュラムをこの教室は全て備えています。あとはあなたの頑張り次第です。
パーフェクトなオンライン音楽レッスン
レッスンではZoomやDiscordなどのコミュニケーションツールや最先端のアプリなど、さまざまなツールを駆使します。
3台のカメラ、デスクトップ共有、資料の共有、リモート操作、サウンドのリアルタイムな共有など、これらを組み合わせて全時代では類を見ないほどの充実した内容のレッスンを提供しています。
また、レッスンの録画も許可しており、実際に対面レッスン以上の効果を実感していただけます。

今こそ、僕たちと一緒に新しい一歩を踏み出しましょう


代表 船橋のりよし:株式会社リクルート『おしえるまなべる』全国8000講座中、全カテゴリー総合年間1位2回、2位2回。スキルマーケット『ココナラ』では販売実績697件、98.7%が★5つ。プロになった生徒は20名以上。挫折させないのが得意中の得意。音楽学校講師として務めた経験も生かし、独自の合理的なカリキュラムで個人指導を行っています。

スキルマーケット『ココナラ』のクチコミ
プロを目指す方へ
ポップス、ジャズ、クラシックの各音楽理論
作曲・DTM・宅録
アレンジ全般・ジャンル特化のアレンジ法
様々な角度からの最新楽曲のメロディ&アレンジ分析
MIDI入力・編集、録音、オーディオ編集、ボーカル修正
本格的なミックスとマスタリング
ギター、シンセサイザー全般
和声・対位法・オーケストレーション
大切なことは、音楽を構成する全ての要素に対して
どれだけ高い次元のスキルを身に付けられるかが鍵であり、
それは講師の力量と熱意、そして生徒の努力、この2つにかかっています。
熱意を秘めた二人の講師が時には励まし、時には厳しくサポートします。
生徒の夢の実現は僕らのミッションのひとつです。
ぜひ同じ目標へ向かって一緒に頑張りましょう。
当教室の卒業生(2024年8月現在)
<J-POP・アニメソング・ゲーム音楽の作編曲>
伊原シュウ(欅坂46、春奈るな、ELISA、刀剣乱舞他)
一之瀬剛(ポケットモンスター全シリーズ)
細見卓矢(アイドルマスター)
田中潤也(龍が如く他)
高森健太(愛内里奈、organs cafe、上木彩矢、北原愛子他)
Minako(雪乃)
shin(ゲーム音楽クリエイター / 大手メーカー勤務)
他1名(Avex Taiwan)
<インストゥルメンタル>
Masafumi Rio Oda(英NOUS RECORDSレーベルよりデビュー)
ino(SUPERNOVA、櫻井哲夫、リスコペルタ他)
<舞台(ミュージカル)音楽>
田中潤也(アンパンマン、しまじろう、マッスルミュージカル他)
丹羽紘子(ザ・シークレット・アクター他)
ino(GEAR)
<映画・ドラマ劇伴>
下石奈緒美(『あんてるさんの花』『あまっちょろいラブソング』『ひかりをあててしぼる』)
ino(『白獣』『市民ケーヴ』他)
<その他TVCM、番組BGM、アプリ、イベント用音楽等>
ino(TV番組各局BGM、大手企業PV)
百瀬いおり
他3名
<プレイヤー、ボーカリスト>
じゅんじまん:Sax(スガシカオ、GRANRODEO他)
寶滿勇太:Bass(CD『ヴォーカル集 遙かなる時空の中で7 紺青の歌』)
伊藤怜美:ミュージカル、バックコーラス(北島三郎、清田愛未、森光子放浪記他)
<シンガー・ソングライター>
宮井紀行
下石奈緒美
篠田沙希
美広まりな
<音楽講師>
高森健太(ギター、ボーカル)
伊藤怜美(ボーカル、ウクレレ)
篠田沙希(ボーカル)
ino(和声、対位法、オーケストレーション、ピアノ)
<その他>
Masafumi Rio Oda:米ワシントン州立大学電子音楽祭、独ザールブリュッケン電子音楽祭などで入選
下石奈緒美:女優(『孤高のグルメ』『オペレッタ狸御殿』『あまっちょろいラブソング』等に出演)
365日いつでも相談可能

シン・東京音楽教室の生徒は、365日いつでもフォーラムを通じて講師に質問や相談をすることができます(完全無料)
質問内容は、レッスンの延長から新しい機材の購入、ソフトの不具合、勉強の進め方まで、何でも構いません。
宿題も完了次第フォーラムに提出し、迅速に添削を受けられ、希望があれば新しい課題ももらえます。
24時間以内の回答をお約束しており、一般的な音楽教室に比べ、圧倒的に効率よく学習を進められます。
当教室では、レッスンの前に無料のカウンセリングを実施しています。
カウンセリングでは、レッスンの雰囲気を体験していただくと同時に、現状や目標、学びたい内容を詳しくお尋ねし、レッスンの進め方や将来必要な機材などについても丁寧にご説明いたします。
このカウンセリングを通じて、今後の音楽の学び方や目標に合ったプランを一緒に見つけましょう。カウンセリングだけでももちろん大歓迎です! 音楽の夢に向けた最初の一歩として、ぜひお気軽にお話しください。

生徒の近況
大手4社から内定を得て、夢のサウンドクリエイターに

DTM甲子園で金賞。次世代クリエイターの快挙


FAQ - よくあるご質問
- どれくらいで理論を習得できますか?
これまでの音楽経験にもよりますが、平均で1年半から2年程度です。
- どのような教材を使いますか?
教材は非常に合理的な内容の、完全にオリジナルな教材を用います。料金は無料です。
- レッスンの録画は可能ですか?
はい、可能です。しっかりと復習できるよう録画を推奨しています。
- 初心者でも大丈夫ですか?
はい、全くの初心者でも大丈夫です。「基礎から丁寧に、あなたのペースに合わせた指導を行います。
- 入会金はいくらですか?
入会金は10,000円です。ただし、12ヶ月連続でレッスンを受講された場合、この金額は全額返金されます。
- 講師はどのような経験を持っていますか?
現役のクリエイターであり、豊富な指導経験を持つ講師がレッスンを担当しています。
- レッスンのスケジュールはどのように決まりますか?
生徒の都合に合わせて柔軟にスケジュールを調整します。曜日や時間帯についてご相談ください。
- オンラインレッスンの環境はどのように整えれば良いですか?
パソコンと安定したインターネット環境があれば大丈夫です。必要なソフトや機材については、詳しくサポートします。
- フォーラムでの質問にはどのくらいで回答が得られますか?
通常、24時間以内に講師から回答いたします。
- レッスン料の支払い方法は何がありますか?
基本的に銀行振込のみとさせて頂いております。
- MPC(作曲イベント)に参加するにはどうすれば良いですか?
担当講師に参加の意思を伝え、参加費500円を月謝と一緒にお振込みください。